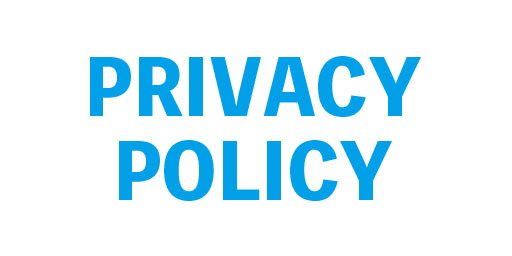■ MOVE ON INTERVIEW vol.4
「映画『親密な他人』の中村真夕監督に訊く」

「俳優さんは何が一番求められるかというと読解力だと思います。自分が意図していたものと違っても、演出家やプロデューサーが、こうしてください、と言ったときに、その意図を理解して、どうのようにお芝居が変えられるか、ですね」
■ 取材・構成:大作昌寿(COOL WIND) 構成補:森内淳(DONUT)
中村真夕プロフィール:16歳で単身、ロンドンに留学。ロンドン大学を卒業後、ニューヨークに渡る。コロンビア大学大学院を卒業後、ニューヨーク大学大学院で映画を学ぶ。アメリカの永住権を持ち、今も東京とニューヨークを行き来して暮らす。2006年、高良健吾の映画デビュー作、「ハリヨの夏」で監督デビュー。釜山国際映画祭コンペティション部門に招待される。2011年、浜松の日系ブラジル人の若者たちを追ったドキュメンタリー映画「孤独なツバメたち〜デカセギの子どもに生まれて〜」を監督。2014年、福島の原発20キロ圏内にたった一人で残り、動物たちと暮す男性を追ったドキュメンタリー映画「ナオトひとりっきり」を監督。2015年モントリオール世界映画祭に招待され、全国公開される。続編「ナオトいまもひとりっきり2020」は2021年山形国際ドキュメンタリー映画祭「ともにある2021」部門で上映される。脚本協力作品としては第45回エミー賞ノミネート作品「東京裁判」 (NHK)29年度芸術祭参加作品がある。最新作のドキュメンタリー映画「愛国者に気をつけろ!鈴木邦男」は2020年の2月にポレポレ東中野で異例の2週間連日満席記録を更新した。2022年には三本の作品、劇映画「親密な他人」、劇映画「ワタシの中の彼女」、ドキュメンタリー映画「ナオトいまも、ひとりっきり2022」が公開予定。

―― 新作『親密な他人』の企画はどのように進んでいったのですか?
中村真夕 元々は、アメリカのテキサスで実際に起きた事件をやろうとしてたんです。行方不明の息子を探している母親のところに、息子のフリをした似ても似つかないフランスの少年が現れる、という実話があって、それを映画化したいと思いました。舞台を沖縄に置き換えたりと、いろいろ準備をしていたんですけど、途中でプロデューサーが次々と変わり、開発していく段階で状況が変わっていきました。高良健吾さんの映画デビュー作の『ハリヨの夏』(2006年公開)の後ぐらいから始めた企画でしたが、お金を集めるのに時間がかかってしまって、成立したのが2020年の夏だったんです。
―― 今作はコロナ禍という設定になっています。
中村 企画が成立したとき、コロナ禍で、プロデューサーと話して、全てコロナ禍の話にしようということになりました。当時はコロナ禍を描いた作品はなかったので、今の現実を描いた方が面白いと思ったんです。今まで、3.11、9.11のような極地的な災害はありましたが、世界中で同じ災害を経験することは、後にも先にも私が生きている間ではコロナだけではないかな、と。みんながそれぞれ孤立感や閉塞感などを感じていたのは、コロナ禍の時期だと思い、その要素を取り入れようと思いました。低予算ということもあって、密室劇の設定だったんですけど、よりコロナ禍で閉塞感が際立ったな、と感じましたね。外でマスクをして、自分の身を守って、家でやっと人と親密になれる感じがしたので、コロナ禍という環境が物語に上手くはまったな、と思います。コロナ関連詐欺などもあったので、それも作品に反映しようと思いました。
―― 社会性や現代における闇がしっかり入っていて、リアリティを感じました。隣で起きてそうな雰囲気がありますよね。
中村 私は帰国子女なんですけど、オレオレ詐欺は日本的犯罪だなと感じていて、海外ではあまり聞かない犯罪なんですよね。息子がお金を無心し、親がお金を出すというのは欧米社会では、ほぼないんです。それが日本の母と息子のいびつな愛情関係を反映しているような気がしました。作品の中で、オレオレ詐欺は日本にしかないんだよ、という台詞も入れました。そういう意味では、私がドキュメンタリーや海外での生活などの経験が反映されていると思います。海外ではオレオレ詐欺の特殊性について注目する人が多かったように思えて、私は、いつも外から日本を引いて見ているからこそ、そういう部分が「見えた」のかなと思います。
―― 映画の反応はどうですか?
中村 今、地方で公開しているんですけど、地方の劇場は(動員が)けっこうしんどいんですけど、評判はいいですね。ただ私は、ドキュメンタリーばかりやってきたので、ドキュメンタリーとは違うのか、と驚かれたりはしています。ただ、カメラマンの辻(智彦)さんは劇映画も撮っているんですが、元々ドキュメンタリーのカメラマンさんで、若松孝二さんの晩年の何作品かを撮っていました。辻さんは、俳優さんのお芝居をドキュメンタリーのように撮れる方で、ドキュメンタリーを見ているかのような気分にさせてくれましたね。
―― 撮影の様子を教えてください。
中村 今回の作品は、低予算なので10日間くらいで撮りました。そこまで無理せずに撮れましたね。朝8時半から午後6時頃まで撮影して、お勤めみたいでした。実際にある築50年くらいのマンションで、変な間取りだったので、それを活かしました。周りは普通の住居なので、遅くまでできないから、21時完全撤収って言われていたんですけど、そのずっと前に終わっていましたね。俳優さんも「待ち」がないから楽だと言ってました。辻さんも現場主義で、俳優さんの動きを見てからカット割りを考えなおしていましたね。絵を当てはめるというより、そこに起こっていることをどう切り取るかを考えてくれるので、そういう意味ではひじょうにやりやすかったです。
―― リハーサルを綿密にやったということですが。
中村 撮影できるのは10日間しかなくて、神尾(楓珠)君にいたっては、忙しいので6日しかなかったんですけど、ワークショップでも毎回言っていますが、私はリハーサルをちゃんとしたいんですよ。ベテランの助監督さんに「日本は現場でほとんどリハーサルをしない」と言われときには驚きました。濱口(竜介)さんみたいに徹底的にリハーサルをやる人もいるので、人にもよりますが、本読みして終わりということもあると聞いて、もったいない、と感じました。今回は現場の時間が短い分、徹底的にリハーサルをしました。例えば、神尾君みたいな、売れてはきているけどまだ芸歴数年の子と、大ベテランの黒沢(あすか)さんのようなレベルが違う役者をどう絡ませたらいいのかということがありますよね? 神尾君の役は、オレオレ詐欺する愛に飢えた子だったので、アクティングコーチに入ってもらい、役の背景と自分の経験を徹底的に紐付けるという作業をやってもらうことによって、神尾君はすぐにスイッチを入れられたみたいです。だから、声高にリハーサルをやった方がいい、と言っています。予算がないならなおさらですよね。
―― リハーサルをやりたがらない役者さんは多いんですか?
中村 リハーサルをやりたがらない人の方が多いと思います。リハーサルをやらないと役者さんの負担が大きくなるんですよね。監督が何を求めているか分からなくて、その場で、やれ、と言われても無理な話だと思います。
―― それで現場がどんどん押していく。
中村 私はリハーサルをやった方が経済的だと思います。
―― 中村さんが映画監督を目指したきっかけは何だったのですか?
中村 父が70年代にデビューした現代史の詩人、正津勉で、母親は美術雑誌の編集長をやっていたんですよ。親が文筆業だと自分もクリエイターになりたいというのはあったんですけど、親と比べられるのが嫌だったので、書く方はやりたくなかったんです。それで最初は絵が好きで、絵を描いていたんですけど、中学校くらいから映画が好きになりました。映画だと、絵と文章の融合と言うんでしょうか、物語と絵で構成されていて、それが自分の一番好きなことだ、と気付いてハマりました。
―― どういう映画にハマったんですか?
中村 私は女子美の付属中学校に行っていたんですけど、当時はタルコフスキーやデレク・ジャーマンとか前衛的な人が好きでした。3本立て映画上映って今はないですけど、学校の帰りによくタルコフスキー3本立てとかをひとりで観に行っていました。6時間くらいあるので、半分寝ながら見ていましたけどね。それで映画館にハマっていきました。まだそのときは映画を撮りたい、というよりは、ただただ好きというだけでした。
―― 映像を自分で撮るのはいつ頃なんですか?
中村 デレク・ジャーマンが好きだったので、高校からイギリスに留学しました。そのときに8ミリフィルムを買って、高校時代の友人と撮ったりしていました。ロンドンにも映画学校はあるんですけど、少なかったので、ロンドン大学の英文学と美術を専攻して、映画研究会に入りました。当時の先輩にクリストファー・ノーランがいたんですが、彼は大学を卒業したあとも、映画学校には行かず、自分で働きながら、週末に映画を撮っていたようです。映研の機材を使いたいから週末は大学によく来ていました。あれよあれよという間に、ハリウッドで有名になっちゃっいましたけどね(笑)。私は大学を卒業した後に、ロンドンの映画学校を受験して合格したんですけど、うちの親に反対されたんです。自分が苦労したから堅気になってほしい、と言われていました。ロンドンにいるな、日本に帰って来い、とまで言われました。
―― その後、ニューヨークに行かれるんですよね?
中村 英文学に行ったときは周りがみんな外国人で馬鹿にされていたんですけど、私は負けず嫌いだったので、アイビーリーグを全部受けたら、たまたまコロンビア大学に受かって。親は詩人のわりにミーハーなので(笑)、コロンビアになら行ってもいい、と乗り気でした。コロンビアか日本帰ってくるかどっちかにしなさい、と言われて。1年だけニューヨークにマスターズ(修士)を取りに行きました。その間に、映画を独学で学んでたんです。最終的にニューヨーク大学の大学院の映画科に入ったんですけど、その時点で親はあきらめたのか、今となっては応援してくれています(笑)。
―― ニューヨーク大学卒業後、最初の映画を撮るまでは大変でしたか。
中村 1本目の映画『ハリヨの夏』(2006年公開)が、京都の舞台の女子高生の話でした。撮るまでに3年ぐらいかかったかな。けっこう早かったですね。当時ニューヨークで、姫田眞左久さんの息子さんと知り合いました。彼は私とは別のニューヨークの映画学校に通っていて、神代辰巳のレトロスペクティブというところで出会いました。その姫田さんとたまたま日本で再会したんですけど、葵プロに入って、企画を探している、と言っていたので、企画を持っていったんです。アルゴという配給会社に助成金を出してもらっていて、当時、葵プロが映画製作を始めたばかりだったため、こちらでやることになり、4000万円ぐらいで作りました。当時は、まだ4、5000万円の映画がありましたけど、今は、1200万円ぐらいが多いですね。
―― 同世代の監督よりは最初の1本に早くたどり着けたんですね?
中村 そうですね。日本に帰ってきたのが31、32歳の時でしたから。でもそこからが大変でした。なかなか企画が成立しなかったんですよ。その間、ドキュメンタリーをやっていました。
―― ドキュメンタリーにはもともと興味があってやっていたんですか?
中村 ドキュメンタリーはたまたまなんです。日本に帰ってきた最初にやった仕事がメイキングみたいな作品で、それまでドキュメンタリーはあまり撮ったことがなかったんですよ。
―― そうだったんですね。
中村 メイキングの仕事をやり始めてから、いろんな現場を渡り歩きました。日本ってこうやって映画を撮るんだ、と勉強になりました。
―― アメリカとは違った?
中村 アメリカとは全然違いましたね。当時は、体育会系みたいなところだったから、人が殴られているところも見ていて。日本の現場は怖いな、と感じていました。怒号が飛び交っていましたからね。今、考えるとあの人達はどこ行ったんだろう、と思います。
―― 中村さんは市川崑さんのドキュメンタリー『市川崑物語』(2006年公開/岩井俊二・監督)にも関わっているそうですが。
中村 岩井さんから「市川崑のドキュメンタリーを撮ってくれ」と言われて、『犬神家の一族』(2006年公開)の現場で、私と『エンディングノート』の監督の砂田(麻美)さんと交代で4か月撮りました。崑さんは、ぼそぼそ喋るので、ワイヤレスを付けたかったんですけど、本人が嫌がるので、監督が座っているモニター前の台の下にワイヤレスを付けて声が拾えるようにしましたね。ひたすら市川崑を観察していて、けっこう面白いかも、と感じました。その辺からドキュメンタリーを撮りたいな、と思うようになりました。岩井さんのおかげかもしれないですね。その後、テレビ番組のドキュメンタリーを撮りはじめて。福島のおじさんや右翼のおじさんを撮って、面白い人が好きなんだな、と感じました。私の中ではフィクションとドキュメンタリーはあまり境がないのかもしれませんね。人を捉えるという意味では根底は同じものかな、と思っています。
―― ドキュメンタリーの難しさはどこでしょうか?
中村 ドキュメンタリーの場合は、リアルな人を撮るわけだから、その人の人生に介入することを意味するので、よりリスキーだとは思います。関係が壊れる場合もありますからね。撮らないでくれ、と言われたこともあります。その人の人生を、ある意味、変えることにもなりますから。ただ根本はドキュメンタリーもフィクションも一緒のような気がします。役者でもドキュメンタリーの被写体でも距離の取り方はだいたい同じですね。仲良くなりすぎると厳しいことを言えなくなるから駄目なんですよ。でも信頼関係はないといけない。手の届くくらいの距離感にいなくてはいけない、ということから言うと、どちらも一緒かもしれないですね。
―― 中村さんが、今、フィクションで描いてみたい人物像はありますか。
中村 いくつかあります。これも市川崑さんや岩井俊二さんから学んだことですけど「常に監督は3つ4つ企画を持ってろ」と言われました。市川さんは亡くなるときも、3、4本の企画を持っていたと思います。だから私も常に4、5本は抱えている状態にしています。競馬の馬みたいに、全部走らせて、どれか先に行くものを撮るという感じです。今やっているのは、ノンバイナリージェンダーやXジェンダーのような、男でもない女でもない人の物語です。日本だと企画を成立させるのがなかなか難しいので、アメリカでやろうと思っています。後は、原作もので熊本を舞台にしたロードムービーです。これは何年か前からやっています。それから、アメリカに住んでいたときにグリーンカードが抽選で当たって、今も維持してるということもあって、今年後半ぐらいからアメリカでの企画を本格的に進めようと思っています。
―― アメリカと日本の両方で企画を進められるのはいいですね。
中村 そのためにグリーンカードをずっと無理して維持してるんです。やっと自分の好きな映画を撮れるようになったのはいいんですけど、日本だと、映画を撮ればとるほど貧乏になっていくんですよ。これがけっこうしんどいんです。アメリカは、間口は狭いので中々入るのが大変ですが、ギャラが一桁違うんです。日本では監督とプロデューサーが一番儲からないんですよね。自分の好きな映画をやっているんだから、お金は貰わなくていいよね、という感じのことを言われたこともあります。アメリカのチケットをせっかく持っているので、これを活かさないのは勿体ないと思って、アメリカで何とかやる術を模索中です。
―― 具体的にはアメリカではどういう動きをしていくんですか?
中村 先ほど話したXジェンダーの企画をAFM(American Film Market)という11月に開催される見本市にピッチすることになりました。去年の11月に『親密な他人』を東京国際映画祭で上映していた傍ら、その企画でTIFFCOMのピッチコンテストにも出て優勝したんです。それでAFMに送ってくれるということになったんです。それから7月中旬にニューヨーク・アジアン・フィルム・フェスティバルで『親密な他人』を上映するので、それに合わせてニューヨークに行きます。旅費も全部出してくれるらしいので、お言葉に甘えます(笑)。そこで一緒にやってくれるプロデューサーを見つけよう、と思っていて、あわよくば、アメリカで『親密な他人』を公開したいな、と思っています。
―― アメリカと日本の現場の違いはどこだと思いますか?
中村 日本ではセクハラやパワハラの問題がいろいろ言われていますけど、労働環境が一番の違いだと思います。今はだいぶマシになってきたかもしれないですけど、例えば、アメリカの場合はみんなユニオンに入っているんですよね。最近、アメリカのテレビ局で仕事しているスタッフさんにお会いしたら、例えばNetflixで仕事するにしても、DGA(全米監督協会)に入ってないとできないよ、って言われました。アメリカは契約社会なので、みんな組合に入ってるんですよね。全部、口約束っていうのは日本だけだと思います。アメリカでは契約をしない限り、誰も動かないです。最初にお金の話や労働条件も全部決めてから動くので、アメリカは働く人が守られている気がします。その代わり製作費は上がりますけどね。日本みたいに、低予算で作品が量産できるのは、その分、人が酷使されてるからできるのであって、アメリカのように、まともに作ってたら量産はできないですね。アメリカみたいにまともに作ると、どうしてもお金がかかる。12時間が基本ですが、それ以降は残業代が時給の1.5倍になるんです。現場が押してくると、みんな裏で計算し始めるんです。そうすると、プロデューサーの顔色が変わってきて、早くしろ、と急かしはじめるんです(笑)。でも、日本だとずっとやってるじゃないですか。アメリカは時間=お金だから、そこはシビアな部分ではありますけど、働く人が守られているところは、やりやすいなと感じます。
―― 最後に俳優さんに対してアドバイスがあればお願いします。
中村 私はメソッド的なことを勉強してきたので、全て自分の経験をベースに、役を取り組むということをやってきたから、いつも俳優さんに言うのは、その人の一番のトラウマ、自分が持っている傷を大事に使え、と伝えます。オーディションとかキャスティングをしているときに思うんですけど、ちょっといろいろあった子の方が、人として面白いんですよね。脛に傷があるというか、自分のトラウマや特性や個性が何かということを知っている人が一番強いんじゃないのかな、と思っています。だから、オーディションのときは「この役と自分の重なり合うところはありますか?」と聞きますね。それから、オーディションやワークショップでいつも言ってることなんですけど、俳優さんって何が一番求められるかって読解力だと思うんですよ。容姿がきれいというのも大事かもしれないけど、その人がどういうふうにこの脚本を解釈して、準備してくるかっていうのを、監督もプロデューサーも見ています。自分が意図していたものと違っても、演出家やプロデューサーが、こうしてください、と言ったときに、その意図を理解して、どうのようにお芝居が変えられるか、ですね。そこを理解していない人は、いくら言っても変わらないんですよ。例えば、5、6歳の子供のオーディションをやったとも、そこを理解している子と理解していない子はけっこうわかるものです。役者さんは特に女性の場合、年齢や容姿が重要視されますけど、サバイブしていくには、その人の読解力、解釈する力が必要だと思います。例えば黒沢(あすか)さんは、全部作ってきますから。姿勢にしても、この役はこうかな、って頭の先から爪の先まで全部作ってくるんですよ。黒沢さんはあえて電車通勤をするらしいです。電車の中で人を観察している、って言ってました。芸能人は車に乗っちゃうじゃないですか。でもそうすると、人が見えないから、役を終えてからから家に帰る途中でいろんな人を見る、と言っていて、子どものときからずっとそれをやっていたそうです。観察力ですよね。観察力=想像力です。目の前に座っている人が一体どういう人で、どんな生活しているのかな、っていうのを、その雰囲気から想像するんです。そういう意味で俳優さんも脚本家や演出家とやっている作業はそんなに変わらない気がします。役作りという部分で「自分じゃない人」を作るわけだから勉強しないといけないんじゃないかと思います。
INFORMATION
『親密な他人』
脚本・監督:中村真夕
出演:黒沢あすか/神尾楓珠/上村侑/尚玄/佐野史郎/丘みつ子
全国順次公開中
公式サイト:https://www.cine.co.jp/shinmitunatanin/